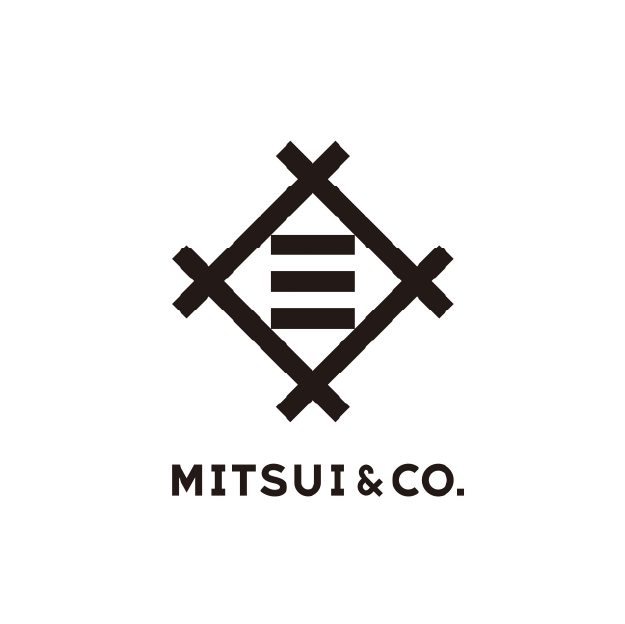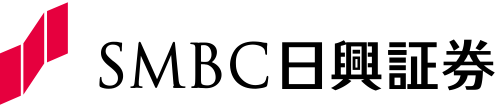最高の
すっきりに、
出会おう。
マインドフルネスをあなたの日常に。
LATEST イベント・ニュース・ブログ
-
 ブログ
ブログアンガーマネジメントとは?怒りをコントロールする効果やコツを解説
-
 お知らせ
お知らせ【セルフ・コンパッション講座 活用編】〜共感疲労への対処法〜
-
 お知らせ
お知らせ【セルフ・コンパッション入門講座(全2回)】〜ホンモノの自己肯定感を育む方法を学びませんか?〜
-
 お知らせ
お知らせ【 青葉の香りを感じながら心も体もゆるますヒントをシェアしようWith Emi】2024/5/19(日)開催
-
 ブログ
ブログマインドフルネス瞑想は睡眠を改善する効果がある?研究事例も紹介!
-
 お知らせ
お知らせ【“How to create a Stress Free life” ~Yoga & Meditation~ by.アンジェラ・磨紀・バーノン】 2024/5/4(土) 開催
SCIENCE
現代社会人を悩ませる、
日常のモヤモヤを解消する。
-
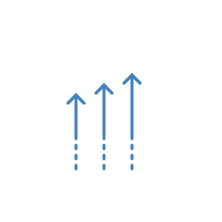
“集中力の改善”
-

“睡眠の質の向上”
-

“脳疲労の解消”
-
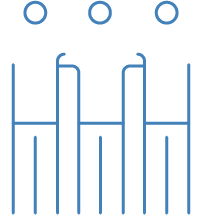
“共感力の向上”
-

“心の安定”
-
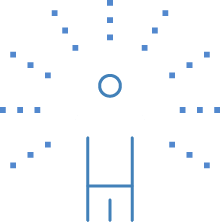
“充実度の向上”
痛みや不安の改善。パフォーマンス向上。
マインドフルネスの科学的な価値は、高いです。
医師(日・米医師免許)/ 医学博士 久賀谷亮氏
マインドフルネスの効能MINDFULNESS
PROGRAM
マインドフルネスを学び、
暮らしへと広げていく。
WHY
MELON
より多くの方に、本当に充実した人生を送っていただくために、
マインドフルネスを日本に、世界に広めていきたい。
そんな“場”を提供することを、MELONは目指しています。

INSTRUCTORS
多彩な経験を積んだ、
知識豊富なインストラクター。
マインドフルネスやメディテーションのわかりやすい説明を通して、
理解と習慣化をガイダンスさせていただきます。

COMPANY
PROGRAM
日本人の“働く”に、
マインドフルネスを。

従業員のウェルビーイングを支える、法人向けのプログラムを実施。
トライアルレッスンから導入や習慣化まで、徹底的にサポートします。
導入企業の一例
INSTRUCTORS
PROGRAM
マインドフルネスを広める、
インストラクターに
なりませんか?

マインドフルネスやメディテーションの基礎知識を学び、資格を取得することで、
より多くの人にその魅力を広めていきたい方に向けた養成講座を開催しています。